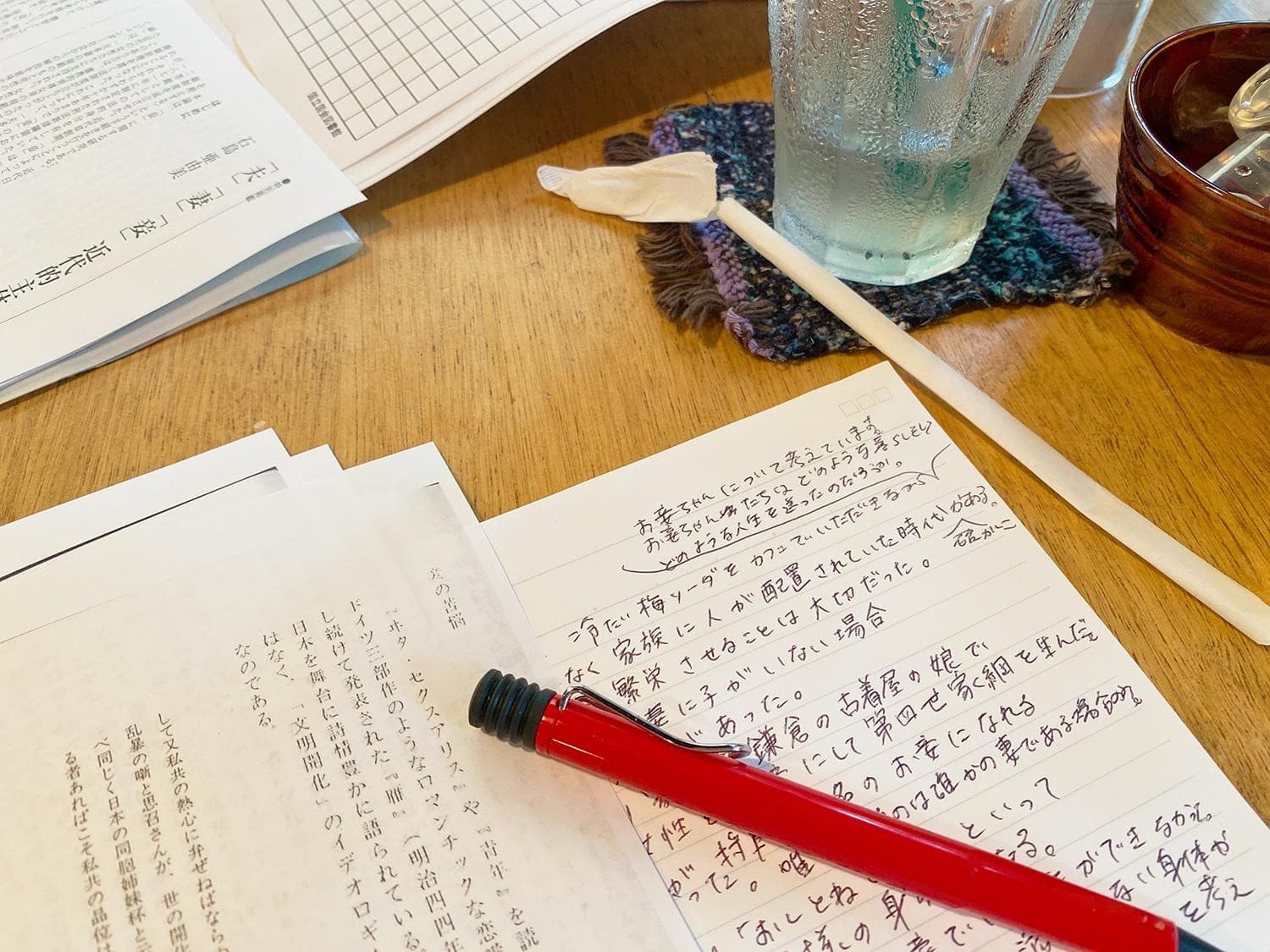
めかけ(妾)
「目懸」とも書く。
“正妻の外にいる妻”をいう。
「目懸」は”目を懸ける”の意で、寵愛することをいう。
《笹間良彦編著「好色艶語辞典」より抜粋》
かつては法の中に「妾(めかけ)」が存在していた。
お妾とはどのような役割だったのだろうか?
世間からはどのような存在として見られていたのだろうか?
今回は江戸期から明治期にかけて「お妾(めかけ)」という存在について考え、彼女たちが必要とされた理由について考えを巡らせる。
《江戸期》子孫繁栄のために
 1825年 歌川国虎《祝言色女男思(しゅうげんいろなおし)》お妾は「囲い者」とも呼ばれた
1825年 歌川国虎《祝言色女男思(しゅうげんいろなおし)》お妾は「囲い者」とも呼ばれたわたしはある土曜日の午後に冷たい梅ソーダを飲みながら、お妾ちゃんについて考えた。
お妾ちゃんたちはどのような暮らしをして、どのような人生を送ったのだろうか。
「人がいてこその家族」ではなく「家族に人が配置される」時代がかつて存在した。子孫を、家族を繁栄させることが重要だった。そのため江戸時代において本妻に子どもがいない場合、お妾に子どもを産んでもらうことがあった。
例えば第三代将軍の徳川家光は、鎌倉の古着屋の娘「お楽」という女性を妾にして第四代の家綱を授かった。由緒正しい家柄の女性のみが将軍や大名の妾になれるわけではなかった。
唯一お妾になれないのは、誰かの妻である場合だ。
また幕府の法則として、妾は一種の「奉公人」であり雇われ人であった。世間体を考え町人に妾の存在を気づかれないように、妾は「御秘蔵(ごひぞう)」と呼ばれることもあった(むしろそんな呼び方したほうが目立つのではと思ったが)。
 (キャプション)1778年 磯田湖龍斎 《色物馬鹿本草(しょくもつばかほんぞう)》
(キャプション)1778年 磯田湖龍斎 《色物馬鹿本草(しょくもつばかほんぞう)》当時の江戸の人々が、お妾をどのように見ていたのかが分かる春画がある。 上の磯田湖龍斎の描いた《色物馬鹿本草(しょくもつばかほんぞう)》の本の中の一図に隠居であろう老人と、その妾が描かれている。
キスマークが付きそうなほど隠居の頬に吸い付きながら男根をしごく妾さんと、顔が溶けるのではないかというほどデレデレのご隠居さん。絵の上部には当時の一般的な妾について書かれている。
一部をご紹介すると、
す
果(くだもの)の部
摺枯(するからし)
気味すつ辛く、嫌味有り
注に渡妾(※わたりめかけ。妾として渡り歩くこと)、囲(※かこい。別宅に住まわせておく妾)、小便組(※大金を受け取り妾になり、適当な時期にわざと寝小便をして主人を怒らせて妾をやめること)の類也。
艶よくして中に実(さね)なし。
隠居、息子をたらす有り。
と書かれており、妾はかなりネガティブなイメージがあったことがわかる。
当時、隠居のひとつの作法に“適当な時期に妾を嫁がせる”ことがあったようで、絵の中の隠居も「そのうち嫁ぎ先を見つけてやるぞ」と妾に言っているが、妾は「わたしは、いやいや。いつまでもお前のそばにいたい。若い男は大嫌いだ。」と言っている。そうやって隠居をたらし込んでいたということを示唆しているのだろうか。
この春画はあくまでも「わらい」の趣向として描かれており、読者は第三者としてこの妾と隠居のやりとりを覗いて楽しんでいるということになるだろう。
- 1
- 2

