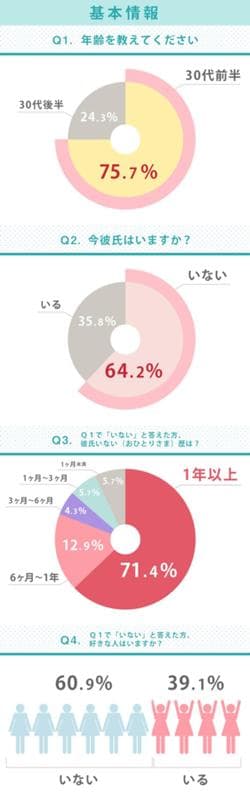「人は欠損に恋をする」
そんなことを考えていた矢先、すごい本に出会った。
『ダーリンは70歳』、漫画家の西原理恵子さんと、美容外科医で恋人の高須克弥さんとの日常が赤裸々に綴られているエッセイ漫画だ。この本の中で高須院長が、美容整形の施術を受けたいと語る西原さんに、こんな風に語っている。
「人は欠損に恋をするんです。黄金律でないもの、弱いもの、足りてないもの、人はそれを見た時本能で補ってあげようとするんです。そして、その弱さや未熟さを自分だけが理解していると思う。欠損の理解者になるんです」
スマホでカメラを立ち上げたとき、期せずしてインカメラになっていて、ふいに映った、緩みきった自分の顔にギョッとすることがある。素の自分ってやばい。だからせめてもの努力で、化粧や小綺麗な服を着てごまかす。
でもよく考えてみれば、これって外見に限った話じゃないのだ。今までどうして仕事を頑張ってきたのかと言えば、必ずしもお金のためだけじゃなく、そうすることで少なからず自分に付加価値がつくような気がしたから。本来の自分が何をどう頑張ってもどこか足りない「欠陥品」であることを、付加価値をつけることで、少しでもカバーできるような気がしたからだ。
一方で、これまで私が好きになった人はみんな、私にとって間違いなく完璧だった。髪がボサボサでも、3日お風呂に入らなくても、精神的に弱くても、コミュ障でも、ずるいところがあっても、その人を構成する、良いも悪いも含む無数の要素が、奇跡的なバランスでその人を作り上げていた。その現象を「完璧」と感じた。
結局、人はそんな風に他者を見て、一言では言い表せない複雑な理由で、誰かのことを好きになるのだ。
好きな人の前で器用さを捨てる
経験と共に身につけた器用さだって、立派に自分を構成する一要素ではあるけれど、本音を包み隠す頑丈な鎧となってしまった場合、鎧が邪魔をして他者はその人の人となりを判断できない。
好き、という気持ちを抱く上で、相手に欠陥があることより、何も見えないことの方がよほど大きな問題だ。だから恋愛においては、年を重ねる中で一旦は器用にしまいこんだ感情を、もう一度そっと取り出さなきゃいけないのだろう。子供じみた嫉妬や寂しさ、爆発的な怒りや、飛び上がりたくなるような喜びを、全部掘り起こして、私はこれです、と堂々と開示しなきゃいけない。弱いところ、だらしないところ、自分のことを好きになってほしい人にほど、見せないといけない。
それは、20代の不器用だったころ、散々痛い目を見て学んできた過程を少し巻き戻す行為。頭の先からつま先まで、隙のない存在でいることを勧めてくる世間一般のモテテクにも反する行為だ。だけど30にもなったからこそ、小手先で惹き付けて、ハレの日だけを共有する相手との恋愛なんて必要ない。
これまでの仕事や恋愛でできたお互いのスネの傷を包み隠さず見せ合って、お、いい傷してるね、って讃え合える相手でなければ、面倒な恋愛をする意味がないのだ。
ここぞというときにこそ、器用さを捨てる。
年を重ね、器用にやれるようになったからこそ、今度はそういうゲームの挑み方ができるはずなのだ。
Text/紫原明子
記事初出:2016.03.10